作詞:坂井泉水、作曲:織田哲郎
「息もできないくらい、ねえ、君に夢中だよ」
歌詞が可愛すぎる。
Medical Association of Clinical Arts
作詞:坂井泉水、作曲:織田哲郎
「息もできないくらい、ねえ、君に夢中だよ」
歌詞が可愛すぎる。
大澤真幸・永井均、『今という驚きを考えたことがありますか マクタガートを超えて』、左右社、2018年
マクタガート「時間の非実在性」
本書は大澤によるマクタガート「時間の非実在性」についての論文の解説、大澤と永井の対談、大澤の「時間の実在性」についての論文という三部構成をとっている。
便宜のため、私たちもマクタガートが何を述べたか、そこから確認していきたい。
ジョン・エリス・マクタガートはイギリスの哲学者で、1908年に「時間の非実在性」という論文を書いた。彼はまず時間上の位置を区別する仕方、時間を表現する仕方には二つあるとし、A系列とB系列とに分けた。A系列は「過去(すでに)/現在(今)/未来(まだ、やがて)」という区別で、B系列は時間的に「より前(先)か、より後か」という区別である。具体例としては、A系列としては「かつて[過去]本能寺で織田信長は明智光秀の襲撃を受けて自害した」という言明が属し、B系列としては「大坂冬の陣の後に、大坂夏の陣があった」という言明が属すことになる。B系列はすべての時点が均質であるが、A系列には、特異点=現在があり、また現在に対して、過去であるか、未来であるかにも、根本的な質的相違がある(p14)。
マクタガートはA系列はB系列よりも基礎的であるとした。時間が存在するためには、変化[ある出来事が未来である状態から、現在である状態を経て、過去である状態になること]が可能でなくてはならない、A系列においてのみ変化が可能である、そうした理由で彼はA系列が基礎的であるとしたのである。
そこから、マクタガートはA系列には矛盾が内在しているから、という理由で「時間は実在しない」と証明する。証明の骨子は以下のようになる。
(1) 「過去である」「現在である」「未来である」は互いに両立不可能な術後である。つまり、これら三つの中のどの二つの組み合わせも両立できない。
ある出来事に関して「過去でありかつ現在である」も「過去でありかつ未来である」も「現在であり未来である」も、いずれも成り立たない。
(2) どの出来事も過去であり、現在であり、未来であって、三つの性質のすべてをもつ。
これは、次のような意味である。ある出来事が「現在である」とする。このことは、その出来事が「未来だった」ということでもあり、かつ「過去となるだろう」ということでもある。つまり、その出来事は、「現在」「未来」「過去」の三つの述語をすべてとる。
同じように、ある出来事が「過去である」とする。そのことは、その出来事が、「現在だった」ということであり、「未来だった」ということでもある。
ある出来事が「未来である」とする。そのことは、その出来事が「現在となるだろう」ということを、そして「過去となるだろう」ということを意味している。
もともとA系列は、変化を可能にする、というところに強みがあった。変化が記述できるためには、すべての出来事について「未来である」「現在である」「過去である」という術後が付けられなくてはならない。
(3) (1)と(2)は誰がどう見ても矛盾している、それゆえ時間は実在しない。
(証明終わり)
これに対する、素朴な反論としては、出来事が同時に過去であり、現在であり、未来であるならば矛盾だろうが、出来事は三つの性質を順番に帯びるのだから問題はないだろう、というものがある。その反論に対する反論は、上記の反論が時間の実在の証明をするときにすでに時間の実在を前提としてしまっているというものである。「かつて、未来だった」といった場合、「過去において、未来だった」ということだが、この「過去において」とか「未来において」とか言うことはそもそも仮定に仮定を重ねることであり、証明において禁じ手であろう。大澤はそうした素朴な反論に対し、マクタガートを擁護する立場からのダメットの再反論としての論証を紹介しているが、くどいのでここでは割愛する。
<私>は存在しないかもしれない
第2部は大澤真幸と永井均の対談である。永井はマクタガートの議論を、<私>論、つまり人称の問題と関係づけている(p37)。マクタガートが論じた時間の問題と人称の問題は、ある意味で同じことなのだと。この場合、<私>に対応するのが、A系列における「現在」となる。
永井は「神はすべてを知っているゆえに絶対にわからないことがある」と論じている。神は全知であるがゆえにわからないことがある。それは、「すべての人にとって世界があるはずなのに、この世界はなぜか<私>に対してだけ現れているという感覚、世界の存在と<私>の存在が同値であるという感覚」(p38)である。「神の無限の知においては、根本的に失われてしまうものがある」(p39)。
「何であるか(〜である)」(本質)と「現にある(〜がある)」(実存)は別のことだが、「出エジプト記」で神は「私は存在するものだ」と答えた。それは、「私は実存することが本質である」、在ることそれ自体が本質であるものが神である、と言ったことになる。しかし、在ることそれ自体が本質であるのは実は<私>である、と永井は言う。デカルトが欺く神の攻撃に対して、「私が『私は存在する』と思ったなら、そのとき私は確かに存在している」と答えた。神とデカルトは合わせ鏡のようになっており、デカルトは、<私>の存在の問題が神の存在との対抗関係にあることをはっきり示した人であるという(p41)。
<私>は、神でさえ識別できないような種類の、客観的には実在しないもので、ただその内側から「これだけが現実に在る」と捉えるしかないものである(p42)。このような事態を永井は「無内包の現実性」と呼ぶ。「内包」というのは、ある対象の集合に関して、その対象が共通にもっている性質を言う。この性質によって、この集合は他の集合から区別されるのである。例えば、痛みを考えた場合、胃潰瘍の痛みと膝の痛みは内包的に区別できるが、<私>の痛みを他人の痛みから内包によって区別することはできない(ベン図を描いたときの共通項がない、と考えるとわかりやすいだろうか)。<私>の本質が実存と一致してしまうというのも、「無内包の現実性」の一種であり、この場合、「本質」というのが「内包」に対応している(p43)。「<私>なるものを定義する内包(本質)は、それが現に存在しているということ以外にはない」。現実性(実在性)はあるけれども、その現に存在しているものを識別する内包(本質)は、その現実性(現に存在しているということ)以外には何もないのだから、これも「無内包の現実性」ということになる。
<私>が<私>について知っていることは、ある意味で、神が神自身について知っていることと同じである。どうしてそうなるかというと、ほんとうは、<私>の持っている「ただ存在するもの」という本性を、人間は神に転移しているからだ。「実存=本質ということを、神に転移したおかげで、人間自身は<私>の存在に驚かないですむ」のである(p44)。
<私>には、「どこまでもある他者との同型性と、それにもかかわらずどこまでもある落差、という二重性がある」(p45)。この落差、否定性を含めて、他人と話が通じてしまう(わかるような感じがする)ことこそが驚きであると永井は言う。
この二重構造はマクタガートが指摘する時間の矛盾に近い。自己と他者の問題と時間の問題はきれいにつながるという(p47)。そして、永井は<私>と現在は同じだと考えている。<私>に言えることと、時間−厳密にはA系列の時間−について言えることがパラレルであると、時制と人称の間に同型の問題をみている。私と今とは同じものだ、同じものの二つの側面だ、とも言える(p55)。
永井はある意味で不思議な矛盾を認めるところからスタートする。矛盾があるから存在しないというのではなくて、「まさにその矛盾がありつつ、存在している」ということろから始まる。マクタガート流に考えれば「時間も私も存在しない」ということになるが、永井としては「存在しないものが存在することが、驚きである」と考えている、と大澤は言う(p72)。
「僕にはこう見えているけれど、君にはそう見えているよね」という視点の互換性を想定しているときの他者の現れ方は、過去的現れ方と似ているのではないか、と大澤は言う。ほんとうは絶対的な差異があるはずなのに、他者を私と地続きで同じような存在と見ている。しかしほんとうは絶対に互換性は効かない。そのように他者が他者性をあらわにしているときは、その他者は未来のあり方をしている(p81)。
私たちの他者への接し方はこのように二種類あり、ほとんどの場合は過去的対し方をしている。このとき、私と他者との架橋不可能な差異が相対化されてしまっている。しかし、ときに、私と他者とのまったく定義できない差異が露呈する。そのときの他者は未来的なものとして現れている。同じ二重性が、時間のレベルでももちろんある、こう考えたらどうかと大澤は提案している。
すべてがわかったときにこそわからなくなるものがある(p85)。永井の議論は、それが人間の最も基礎にあること証明している、と大澤は言う。さらに、永井は実は、神のほうが実在を捉えていて、<今>とか<私>とかは実在しないのではないかと結論づける。
大澤真幸「時間の実在性」
第3部は大澤による「時間の実在性」の証明である。
大澤は上述したような永井の洞察も踏まえ、<私>:他者=<現在>:過去(または未来)という比例式をまず示し、<私>(と他者)や人称性という角度から、時間に迫っていく。
大澤の問いはこうである。どうして、<私>は、他者もまた<私>であることを知るのか。ここで、他者がまた、それ自体、独自の<私>でもあるような状態として現れているとき、その他者を<他者>と表記するとこう問うこともできる。この<私>にとって<他者>は端的に存在しない、ということは事実であろうか?
ここで大澤はレヴィナスの<顔>を参照する。レヴィナスが<顔>と呼んでいるのは、一般に、<私>が眼差しているとき、この<私>を眼差す(眼差しを返してくる)対象の一般である。つまり、<顔>は、<他者>の一種である(p115)。<顔>の変奏が<皮膚>である。すなわち、<私>が触れているとき、<私>が触れる対象こそが、<皮膚>である。レヴィナスは、<顔>や<皮膚>においては、「そこにあるもの」が「そこにないものであるかのように」求められる、「現前(=現在)」と「現前からの退却」とが同じことになってしまう、と述べている。
愛撫とは、<私>が触れる皮膚が、<私>の皮膚や指へと触れ返すものとして、つまりそれ自体、応答するものとしてある、ということである。だが、<私>が触れているそれを、何ものかとして把持し、同定したとたんに、「それ」は、<私>に触られるだけの対象へと転じてしまう。レヴィナスは「愛撫とはなにも把持しないこと」だという。<私>が触れ、そして<私>へと触れている「それ」を、<私>が何ものかとして同定し、<私>へと現前(=現在)させようとしたときには、「それ」は、もはやそこにはないものとして、つまり退却してしまったものとして現れるほかない(p116)。
<顔>についても、<皮膚>と同様のことが言える。<私>が、他者の<顔>を見ているとき、<他者>は、つまり<他者>のまさに<他者>たる所以(他者の<私>)は、すでに、(<私>への)現前から退いてしまっている。このような<他者>の逆説的・否定的な現前の様態を大澤は「遠心化」と呼ぶ。他方、<私>に帰属している、知覚や感覚を含む心の働き、<私>が見たり、感じたりしている、この状態を<私>への「求心化作用」と呼ぶ。
<他者>は、<私>に対して遠心化作用を通じて現れる。<他者>の痛みは<私>にとって痛くない(<私>は<他者>を直接には知覚できない)、このような不可能性を媒介にして、<他者>が、<私>に対して開示される。
このような遠心化作用によって、<他者>はどこに去ったのか?<他者>はすでにいない。ということは、かつてはそこにいた、ということでもある。すなわち、<過去>へと去っていったのである、と大澤は述べる。ここで、時間という主題へと回帰する。
<他者>の存在の様態−「すでに(去った)」という様態−が、「過去」なるものを存在せしめる。「過去」がまずあって、<他者>がそこに逃げ込むのではない。逆に、<他者>の、<私>からの退却のベクトルが、過去という時制を切り拓くのである(p119)。<他者>は、常に、<私>が見出す状態よりもわずかだけ余計に死に近づいている。<私>が直接に見るのは、<他者>が去ったあとの痕跡である(p120)。このように<私>と<他者>の間の差異は、「現在/過去」と、時間的なずれという形式をとる。この不可避に生じる時間的なずれを、レヴィナスは「隔時性(ディアクローニー)」と呼ぶ。
上述したように、<他者>の逆説的な現れが、過去の存在を可能にする。こうして、過去を実在的な次元として言及、活用することができる地点に到達した(p120)。ここで、大澤はこれまでの考察の成果を、ジル・ドゥルーズの「純粋過去」の概念へと接続する。
純粋過去とは、「すべての出来事が蓄積され、去り行くものとして記憶される、絶対的過去」である。純粋過去は、いわばヴァーチャルな過去である。どういう意味でヴァーチャルかと言えば、純粋過去は、まだ現在であるような出来事をすでに含んでいるのだ(p121)。
たとえば、大澤が「私は今、マクタガートに対抗して『時間の実在性』を証明する論文を書いている」という言明をするとき、この言明には、すでにほんのわずかではあれ、過去の出来事の回想というモードが含まれている。つまり、現在の出来事は、自らを「過去」の一部として知覚する、まさにその限りにおいて、現在の出来事である自己自身を認知することができるのだ。同じことが、過去の出来事や未来の出来事についても言える。どの出来事も、自らを、「過去」の一部として認知するほかない。このカギカッコで記した「過去」こそが、純粋過去、あらゆる出来事の認定を可能にするアプリオリな形式としての過去である、という(p123)。
そうだとすると、出来事は現在でありかつ過去である、ということになる。しかし、これこそ、マクタガートが指摘した矛盾ではないか、やはり、時間は実在しないと結論せねばならないのか?違う、と大澤は言う。「今やわれわれは、その出来事が現在であり、同時に過去である、ということをためらいなく堂々と言うことができるところに来ている」と。なぜか?それは、上述の「<他者>の実在性」についての証明があるからだ。<他者>の現前=現在)とは、その過去−「すでにいない」「かつていた」−でった。<他者>の実在において、われわれはもう、現在でありかつ過去である−過去であることにおいて現在する−という様態を認め、導入していた。ゆえに、「出来事に、現在であるという規定と過去であるという規定をともに付けることに何の問題もない」と。むしろ、そのことが、<他者>の実在と同様に、出来事の時間的な実在を可能にしていると。「出来事は、まさに現在でありかつ過去である。そのことゆえに、時間は実在する」と大澤は結論づける(p124)。
さて、大澤はここからさらに、決定論に対する自由の優位性を回復すべく論旨を進める。自由と決定論との関係については、非両立主義と両立主義がある。非両立主義は、われわれの「自由」と「人間の行為もまた自然の決定論的な因果関係の中に組み込まれているという観念」とは両立できない、とする考えで、これは科学の世界観と整合性を保つことはできない。非両立主義は、自由が帰せられる何らかの実体−人間という主体等−が、因果関係のネットワークからなる現実の外部にいる、と見なしており、要するに、人間に創造神の性質を(部分的に)与えていることになる。これは、科学的な合理主義の受け入れるところではない、という(p125)。両立主義は、これに反対して、自由と決定論的な主張とは共存しうる、と述べる。しかし、その際に基礎をなしているのは、決定論のほうであり、決定論の中で、自由(という意識=幻想)に存在の余地を与えること、これが両立主義であるという。自由は決定論に対して従属的な位置に置かれる(p126)。
大澤の論旨を振り返ると、現在の出来事は、自身を過去の一部として知覚することを通じて、まさに現在の出来事になる。このとき、現在の出来事そのものを「過去」として知覚する視点こそが、未来に属している。未来に措定された視点がなければ、現在の出来事が過去として現れることはない。ということは、未来の視点をどのように設定するかによって、現在の出来事の同一性(アイデンティティ)が、つまりこの現在に何が起きているのかということが、異なって現れてくる、ということでもある(p127)。
「目下の現在を知覚する未来の視点は、すでに完了した現在−つまり過去の出来事−にも影響を与える。つまり、どのような未来の視点から現在を見ているのかということは、どのような過去の出来事があったのかという認識をも規定している。現在を過去の一部として見返す未来の視点は、その現在の出来事へと連なっている過去に何があったか、ということをも規定する」(p127)。現在の出来事が過去の出来事にトータルに因果的に規定されている、という決定論の主張は全面的に正しいが、「どの過去の出来事(たち)が現在のこの出来事を決定しているのか。どの過去の出来事の因果的な連鎖が、現在の出来事へとつながっているのか。このことを規定しているのは、現在の出来事と過去の出来事とを遡及的に見返す未来の視点である。どのように未来の視点を措定するのか、というところに、自由が関与している。原理的には、未来の視点はどのようにも設定できる。この未来の視点が、決定論的な連鎖そのものを選択している」。これは、「決定論を基礎にした両立主義ではなく、逆に、自由の方に基礎をおいた両立主義になる」。
未来の未来たるゆえんは、絶対に還元できない不確定性である。どうしても解消できない不確定性があるということ、これが未来の定義的な条件である、と大澤は言う。この不確定性は<他者>を規定する条件でもある。そして、<他者>には、本源的に自由が所属している。こうして見ると、未来を未来にしている条件と、<他者>を定義する条件とは、同じものであることがわかる。とすれば、未来とは<他者>であり、<他者>は、その本来性においては未来なのだ、とこう断定してもよいのではないかという(p129)。
「<他者>の他者性が生(なま)のままに現れているとき、<他者>は『未来』として現れている。その<他者>を同定し、その不確定性を縮減しようとするとき、<私>は、必然的にそれに失敗する。その失敗は、『過去』という痕跡を残す」(p130)。
「自由は、現在と過去とを遡及的に見返す未来の視点を設定する営為のうちにある」。このことは、「自由が<他者>との関係のうちにこそある、ということを意味している」(p130)。
神の視点と人間の視点
以上が本書の概要である。マクタガートの「時間の非実在性」の証明は神の視点からの証明、大澤の「時間の実在性」の証明は人間の視点からの証明と考えると見やすいだろうか。第2部の対談で大澤は「神の無限の知においては、根本的に失われてしまうものがある」と述べ、ここに永井の発見があるいう。この根本的に失われてしまうものが、時間であり、<私>というものだろう。
「すべてがわかったときにこそわからなくなるものがある」という大澤の発言も同じ事態を示している。
このような見方は、「この世界のすべてのものが、近くで見るとぼやける」と言うときの量子重力理論の研究者であるカルロ・ロヴェッリの発言とも共鳴するように思える。「わたしたちはこの世界を大まかに切り分け、自分にとって意味がある概念の観点から捉えているが、それらの概念は、あるスケールで『生じている』のだ」(カルロ・ロヴェッリ. 『時間は存在しない』. 冨永星(訳). NHK出版. 2019.)
時間とマクロな平衡状態の関係を解釈する際には、標準的な理論では「時間→エネルギー→マクロな状態」となり、マクロな状態を定義するにはエネルギーを知る必要があり、エネルギーを定義するには時間の正体を知る必要があると考える。しかし、同じこの関係を別の角度から捉えることができるとカルロ・ロヴェッリは言う。「マクロな状態→エネルギー→時間」と逆に読むのだ。「マクロな状態を観察すると、この世界のぼやけた像が得られるが、それをエネルギーを保存するような混ぜ合わせと解釈することができて、そこから時間が生まれる」と。「時間が決まるのは、単に像がぼやけているからなのだ」。「時間の進展が状態を決めるのではなく、状態、つまりぼやけが時間を決めるのだ」。このように「記述の不完全さ」があればこそ、時間はあるものとして解釈できる。
ある人は英語の過去形は「遠い形」と呼んだほうがいいと言う。過去形は「遠い形」で表現される中の一つでしかないと。そういう意味では現在形は「近い形」である。いずれも<私>を起点とし、<他者>との関係性、距離の取り方を問題としている、ということだろう。未来形というのは自由意志を前提としており、今の私の意志の表明でしかないとも言えるかもしれない。
解離は<私>を起点とすることをやめることで、時間の非実在性を証明し、忘却の中に自ら飛び込む行為かもしれない。未来的未来は語りようのない、不確定なナルホイヤ的(イヌイット的)未来だろう。
純粋過去としての未来、過去的未来(<他者>としての未来)を起点にすることで、私たちは自由を取り戻すことができる。別様の因果の連鎖を選択することで。
純粋過去としての未来からの眼差しは、時間の非実在性を否定しているわけでもないだろう。遠い彼方で雨が降っているのを私が見るとき、それは現在であって、過去であって、未来であるとも言え、それを時間の非実在と言うこともでき、我に帰ると時間の実在でもある、ということだから、分析哲学的には反論の余地はいつまでもあるだろうが、実在しつつ実在しないということは全く不思議なことでもない。私が自由に眼差すときはいつも、過去として、未来から眼差すのであって、そこで私は他者であると同時に私であり、眼差しもまた他者であると同時に私であるものへと向けられつつ、向けているのだろう。
私は子どもが怖い。彼らの社会的な人格は未熟だが彼らの自然の威力は大きい。
彼らの自然は複雑で彼らはそれを表現する術を知らない。あらゆる理不尽な形で私たちを試す。私はその表現がわからない。彼らをどうすればいいのかわからない。
岩宮恵子の「生きにくい子どもたち」をI先生に薦められて読んだ。一対一の土壇場で彼女はどうやって生き抜いてきたのかわからない。
「普通」の人々が、大きな労力を払い続けて「適応」し続けていることを思う。
広瀬香美が「ゲレンデが溶けるほど恋したい」歌の中で性格変えた方がいいかもよと言う。「普通」の人々は適応するために労力を費やして性格を変えることができるのかもしれない。元の自分というものが死んでいくことの恐怖に耐えることに慣れていく過程が適応なのかもしれない。
果たしてこの世の中は適応する価値があるのかと思い続けてきた。神社、カトリック、一部の寺、本屋に生かされてきた私には現実界は痩せて見える。私は適応していないからだ。適応していないから毎日苦しみがある。普通の人々は適応しようとしない私を無意識的に憎しみ侮蔑し無関心になるかもしれない。
岩宮恵子氏は異界に片足を突っ込みながらどうして異界の子どもたちの助けになれるのかわからない。驚異的な知能と体力と精神力の持ち主かと思う。
私はいよいよ怖くなった。
私は頭で考えると間違う。良いように導かれることを祈り求める。
空谷子しるす
上間陽子、『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』、太田出版、2017年
本を買ったのはいつのことだったか、4、5年読んではやめてを繰り返していた。
沖縄でキャバクラや援助交際をしている少女たちを取材した記録だが、著者はその原稿を本人に読み上げ確認してもらっている。だからこれは彼女たち自身へのメッセージも込めて書かれたものでもあるだろう。社会学で語られる大文字の言葉は使わずに書かれている。
沖縄の男だけが、というわけではないだろうが、どうしようもない男たちがたくさん出てくる。DV、レイプ、彼女に援助交際をさせる男、等々。
安心できる居場所を彼女たちは自分で探さなければならなかった、裸足で逃げるしかなかった少女たちの記録。
読んでいると、こども食堂をしたい、寺子屋をしたい、図書館をしたい、バーをしたい、全部一緒にやってしまいたい、という衝動がおさえがたくわいてくる。
バーテンダーというのは優しい止まり木という意味らしいが、止まり木が、居場所がないのは何よりつらい。
話したくないことは話さなくていいし話したいことは話せばいい、そういう居場所をつくりたい。
著者はこの本を、子供が寝静まった深夜に書いていたという。私も家族が寝静まった部屋でこれを書いている(どうでもいいだろうが)。言いたいのは、社会学的な調査であっても、書かれたものは本来書き手の生活とは切り離せない。切り離せるとしたらそれはもうただの稼業でしかない。彼女はそれをわかっていて、ただの調査対象にできないこともわかっていて、生活を見届けた上で書き始めている。簡単に終わらせるわけにはいかないから。
沖縄の夜はどんなに暗いだろうか。
沖縄にかぎらない。どうしようもない男と書いたが、人ごとではない。男はメタファーにもなり得るが、どうしようもなく男だ、とも感じる。
どうしようもなくどうしようもない男だ、それは誰も人ごとではない。
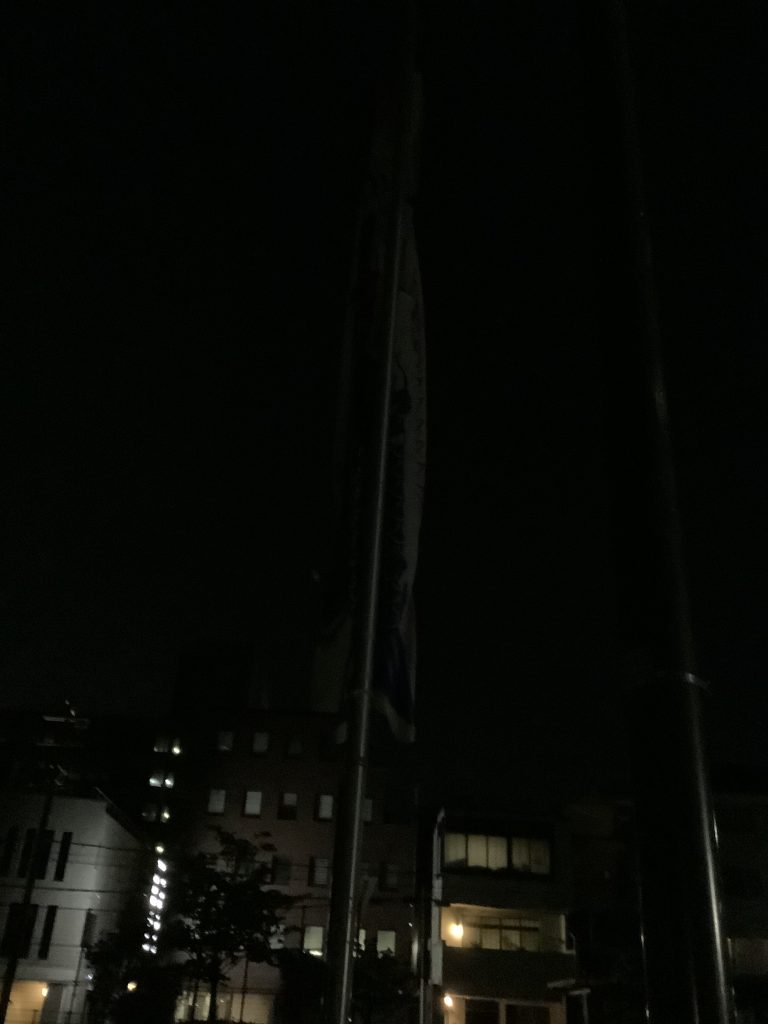
安野侑志、髙田真理、『世界一の紙芝居屋ヤッサンの教え』、ダイヤモンド社、2024年
ヤッサンは紙芝居屋さんで今は息子さんのだんまるさんがその意思を引き継いでいる。この本自体は弟子の始毱さんがお師匠の言葉を集め、教えとしてまとめたもの。
教えのいくつかを以下に書き留めておく。
一所懸命やる
「心構え」ではなく「心が前」で臨む
話し合いではなく話試合、まるくおさめるんじゃなく三角におさめていく
過ぎなければ及ばざるが分からない。行き過ぎたら、ちょっと戻ればいい
しょうもないことをたくさん言え日記ではなく日死。一日の葬式、心のオシッコとして書く。一日一日生まれ変わるため
8時間の「自分時間」を確保する
蟻の一穴をあちこちからあけておけばいい。機が熟する、そのときまで
真愛(間合い)。本当の愛というのは相手に伝えるために間を空ける。相手を気遣い、相手の様子を一瞬確認すること
変でもいい。変なものが出てこないと、ずば抜けて面白いものは作れない
9歳の年輪を残した「おとな」になれ。年輪を響かせて、そこから新しいものを生み出していく
世の中そんなに辛く(からく)もない
やりたいことをやるには、いかに「やりたくないことはやらない」でいられるかに尽きる
今日一日をどれだけ大きく喜べるか。今、この瞬間を生きて、未来への「未知の道」を進むのだ
「話し合いではなく話試合、まるくおさめるんじゃなく三角におさめていく」あたりはオープンダイアローグにも通じるものがあると思った。
日死、心のオシッコは私もしてみようと思ったが、怠惰ゆえにできないかもしれない。
間合いでなく、真愛。その一瞥、一瞬のまなざしに真実の愛を感じる。
しびれます。
夢日記を自動で作成してしまう人工知能ができたら、私は夢を一生懸命思い出す努力をしなくて済むようになるだろうか。夢には飛躍がある。ツェズール(休止符)というらしい(中井久夫)。人工知能はツェズールをどう処理するだろうか。ツェズールのある夢が健全な夢である。悪夢にはツェズールがない。もし人工知能がその飛躍を取り繕い、休止符のない物語に仕立て上げるのであればそれは悪夢である。
病院ですることはたいてい人工知能で事足りる。機械的診断や機械的処方なら人工知能のほうが間違いが少なくて良いくらいだろう。眠れない?眠れる薬を出しましょう、増量しましょう、種類をかえましょう。声が聞こえる?幻聴を和らげるお薬を使いましょう、増やしましょう、もっと良い薬を試してみましょう。症状ベースで薬を出すことは人工知能の得意とするところだろう。精神科医はいらない。
本書の中で薬物療法の項があるが、薬物についてはほとんど語られない、むしろ訪問診療では病院で診療しているときも薬を処方しなくて済むことが多いという。環境調整やリハビリなどが第一の処方になるようだ。社会的処方という言葉もある。紙にどうしたら良いか書いて渡すことがある。これも処方と言えないこともない。その紙をかかりつけ医に見せたら、これが紹介状かと激昂した医者もいるとかいう。
私が子供の頃、祖父に何か言葉を書いてほしいとせがんだことがある。祖父は真実一路と紙切れに書いた。心に響いたかどうかは別として、ずっと覚えている、これも処方だろう。遠い未来に届けられる言葉もある。病棟に頼らない、地域を耕すとはどういうことか。まず、患者を地域へ移行させるのではなく、まず医療者から地域移行を図ること。ただ追い出して受け皿もないというのでは困る。患者が地域住民に慣れるのではなく、まず地域住民が患者に慣れる必要もある。
NPO法人は地域と医療を結ぶ架け橋になることができるかもしれない。健康カフェでも、不健康カフェでもとっかかりはなんでもいい。結び目を作っていく。医療とだけではない。教育も。子供との結び目も作りたい。教育はするだけではなく、されることも含んでいる。一方的ではなくSide by Side(横並びの関係)がよい。収益を回すことも考えたい。NPO法人で得た利益を衣食住が足りない人へまわせたらよい。YOUTUBEなどへ投稿した学習動画などから得られる広告費などは微々たるものだろうが、潔癖である必要はなく、自分たちのお小遣いとはしないようにだけ留意して必要なところへ再分配できるようにする。困った子供たちや大人のための寺子屋、駆け込み寺のような場所でもあってほしい。思春期の相談窓口でもあってほしい。そこへ訪問看護ステーションと医療法人も結びつける。親も子供もまとめてみる。住民として住民をみる。これは近所のおばさん、おじさんprojectと言ってもよいかもしれない。
何も神さままで引っ張り出してくる必要はない。ほどほどの超越していない他人こそ時の氏神となることがある。私は間抜けな近所のおじさんでよい。病棟に頼れなくなったことで症状がかえって軽くなったという。頼れないからこそ、ということがある。病院は精神医学化した患者を作る。患者を精神医学化せず、地域の住民として、おじさんとして、ちょっと偏ってはいるがものをある程度は知っているらしいおじさんとして結び目を作っていく。
私はどうしてもリゾームを想起してしまう。樹木のような縦の繋がりではなく、横の繋がりで、分野さえも横断する、それでいて土壌ごとに繋がり方は異なっていてよい、むしろ地域ごとに相応しい繋がりを模索すべきだろう。本書の中で言われる地域を耕すとはそのような根茎方式で地域の単位で適切な社会的紐帯、共同体を形成していくことではないか。決してトップダウンとはせず、かといってボトムアップにある地域で成功したモデルを他の地域でも適用していく、というわけではない。地域ごとの最適解、最も相応しい繋がりを、他所からみたらいびつにみえてもその地域によってはこれが一番落ち着くのだという場を形成していくこと、これが言うなれば地域ごとモデルとして現実的で実践的なスタイルなのではないか。
地域ごと、というのは小さく見えたとしても大きな価値観や倫理観の転換であると思う。これはまるごとアートの領分でもある。地域ぐるみで取り組む壮大なアートであろう。
休止符がない夢は悪夢であると言った。人工知能は夢や創作をある種の悪夢へ落とし込んでしまうかもしれない。地域ごとモデルに人工知能の入り込む余地はない。それはおじさんでもおばさんでも子供たちでもよいが私たち住民にしかできないことである。地域というアートを作るのは病院でも企業でもない、医者でもない、私たち住民の繋がりである。
本書は地域で精神医療や医療だけでなく、地域から文化の復興を考えているすべての人にとって参考になるだろう。少なくとも地域の医療にとって医者は中心的人物とはならないしなるべきでもないということが読めば実感できるだろう。病院での序列は忘れたほうがよい。ソーシャルワーカーが、薬剤師が、看護師が、作業療法士が、或いはその人の生活を最も打つことになるかもしれないし、本当は誰がというのではなく人がいつのまにかそのコミュニティの中で癒されているという在り方が最も良いのだろうと思う。困った時はお互い様というように。そこでは誰が誰に何をが消失している、それなのにいつの間にか良くなっている、或いはどうでもよくなっている、問題ごと消失している、ということがあってよいだろう。
ピーター・スコット-モーガン『NEO HUMAN ネオ・ヒューマン: 究極の自由を得る未来』
久しぶりに実家へ帰ってきた。前回来たのはもう一年以上前になる。玄関にはピンクの柵が立てかけられており、来客は柵を跨がないと入れなくなっている。それはもう十年以上も前からずっとおそらくそのままだった。犬が二匹おり、柵をしておかないと庭に放したときに、玄関を抜けて全速力で駆け出してしまうから。家の前には田園が広がっており、1kmくらい先までは見渡せるかもしれない。犬が逃げたらすぐに見つかることが多いが、田んぼの反対側はすぐに道路になっているため、反対側へ向かうとはねられてしまう危険も高い。犬がまだ小さい頃はよく脱走して、皆で探し回ることもあった。最近そういう話は聞かない。もともと三匹だったが、昨年白いトイプードルが老衰でなくなり、茶色いトイプードル二匹となった。
来客はピンクの柵を越えるか、横の駐車場から中に入るしかない。内玄関までは石畳となっており、左側には中庭のような空間がある。芝が生い茂って、ずっと立ち入ることも難しいくらいだったが最近人工芝をそこに被せてゴルフの練習場にしたらしい。球を数メートル先の的へあてる程度の簡素なものだが。
次女が来るのは初めてだった。母を見ると辛そうな顔をして泣き妻を手探りで求めた。長女は初めてではないが、だいぶ久しぶりのことでかしこまっていた。長女は4歳、次女は1歳になる。ここへ来る数日前から長女は妻の実家へ滞在していた。妻の母が京都まで迎えに来て新幹線で連れて帰ったのだった。長女はホームシックにかかることもなく毎日楽しく過ごしていたようだった。妻の妹の子供が二人おり、プールをしたり自転車に乗ったりして遊んでいた。長女はまだ自転車には乗れなかったが交通公園で練習して補助輪付きだが一日で乗れるようになったとのことだった。
私の実家に来た長女は姪っ子と別れがたかったようで、彼女のところへ帰りたいと泣きながら訴えた。私の実家にもあと2、3日で姉の子供たちが来ることになっていたが、今は周りも大人だけということもあり姉の子供たちが来るまでは子供たちと妻は妻の実家で過ごすことになった。
ピーター・スコット-モーガン『NEO HUMAN ネオ・ヒューマン: 究極の自由を得る未来』はまだ予約の段階で姉に教えてもらってamazonで購入した。車の通勤中に2/3くらいは読んでいたが、残りを一人になった時間で読むこととなった。ピーターはALSに罹患した。経歴や粗筋は調べたらすぐに出てくると思うので割愛する。端的に言うと、ピーターは人間とAIとの融合を目指している。人間としてのピーター、つまりピーター1.0からサイボーグとしてのピーター2.0への変容を遂げること、そして人間の生物としてのピーターの死後はAIのピーター3.0として生き延びること。2.0は現実の世界を生きながら、仮想現実としての世界も同時にVRのゴーグルをつけることで生きることができる。そこでは五体満足で魔法さえも使うことができる。2.0はまた現実の世界に遍在するようになる。生物としてのピーターがどこにいようと、2.0は講演会を複数の場所で同時に別の言語で行い、存在することができる。AIはピーターと融合しているので、ピーターというアルゴリズムを学習してどこにでも同時に存在し応答できるようになるというわけだろう。
私はまだ観たことがないがAIとかバーチャルリアリティといえば映画のマトリックスを想起する方もいるだろうか。私はこういう話を聞くとつい90年代後半に放映されたアニメ『serial experiments lain』(1998年)を思い出す。レインは現実の世界とワイヤードというコンピュータネットワークの世界に遍在する。現実の世界と仮想現実を往来できるのはそもそも人間が発する電磁気によりコンピュータの端末として中継となれるからである云々といった話だったと思うが、すでに子供の頃の記憶なので曖昧である。
ピーター2.0が目指しているのはレインなのだろうか。AIの予測変換の究極は意識の共有だろう。それが伝達速度としては原理的に最も速い。Wired Brainについてはジジェクも言及している。その是非はわからないというか、機械と脳を接続することは今後何かしらの形で可能になるだろうしその流れを止めることもできないだろう。そしてWired BrainなりAIと人間/脳の融合が普及すれば確実に倫理の再構築も求められる。というよりも今からすでにその時に備えておく必要があるだろう。
すでに現実となる前からピーター2.0を受け入れる下地はできていた。Googleに代表されるインターネットサービスはモニタリングし個々を繋ぐことで自他の境界や絶対的他者の存在を不明瞭なものとし、レインの世界観の基底にある集合的無意識とかユング的世界観に傾斜していくポテンシャルがある。
問題はそうしたときに如何に他者性や責任を担保していくか、ということだろうか。ピーター2.0や3.0は何も新しい問題ではない。人と簡単に繋がることができるようになったということは、繋がらずにおくことが難しくなったということで、卑近な例では携帯電話が普及したおかげで仕事がサボりづらくなった、もっと遡れば車が普及したおかげで労働に従事する時間が増えてしまったということでもある。テクノロジーと接続は切っても切れない関係にあるかのようだが、切断のテクノロジーのことも今後はもっと考えていく必要があるだろう。単に個人の選択でtwitterをしないとかfacebookをしないとかいうことではなくテクノロジーの次元で接続解除するということ。
自宅の本棚にはもう10年以上前に購入した本が無造作に並んでいる。本は色褪せる。中身の問題ではなく、物理的に文字通り色褪せ埃に塗れている。電子書籍やバーチャルリアリティは古くなることができない。
実家の引き出しに指輪が入っていた。内側の刻印を見るともうすっかり忘れていたが、2007年に作製されたものらしい。もともとシルバーのリングだったのだろうが、今では錆び付いて黒々としている。子供たちはまだ帰ってこない。体操教室に連れて行ってもらっているらしい。妻の電話の向こうで笛の音と子供たちの声が聞こえる。犬はいつものようにリビングのソファでうたた寝をしている。
褒められぬ。
人から求められぬということはつらいことである。
子供じみた悩みといえばそうだが、人間はすべからく子供じみていることは八十、九十歳の人々を見れば容易に気がつくことだ。
自力でなんとかするというのは虚構である。
虚構であることを若いうちは思わぬから、歳をとったあとに余計に子供じみてくる。
歳をとってから、死ぬ直前に、自力が虚構であることに気づくよりは、若いうちから己の無能に苦しむほうがましである。
己の無能に悩むことは、生まれてからずっと続く生き地獄である。
己の無能によって、まわりに理解されることは無理である。まわりに求められることも無理である。まわりは己の無能を憎み卑しむ。だから己をまわりから自ら截断し、閉じこもり、あほになる。
龍膽寺雄は戦前戦後の作家である。
塗炭の闇のなかにあってサボテンのことばかり考えていた作家である。
文章がうまい。
「仕事という仕事は、––小説書きでも、学問や研究でも、金儲けでも、人間臭さの中でおこなわれる。このようにして世に生きて、自分がはき出すハナ持ちならぬ臭気に自分で背を向けたいからこそ、ひとり静かに植物の一と鉢もいじってみたくなるのだろう」(空想独楽)
大変前向きだ。世間をうっちゃってサボテンを育てることほど前向きなことがあるだろうか!
怠け者の堕落と前向きな行動とは紙一重である。
自力が虚構であることを知るものは道楽に走る。
道楽に真摯になれば道に至る。
道に至れば人間は満足である。
修羅は絶滅せよ。龍膽寺雄に誉れあれ。
道楽を邪魔する魔障は調伏されよ。
空谷子しるす
他者をどう考えるかという問いに対して、三島は「私の大嫌いなサルトル」という言い方をして『存在と無』から最も猥褻なのものは縛られた女の肉体であるという文言を引用し、エロティシズムと暴力の必要性について語っている。ここでいう他者というのは、双数関係にある他者ではなく、大いなる他者であろう。それを三島は天皇という。
他人を物のように扱うことの誠実さは他人の中に自分を見出さない、他者は自己の鏡ではない、という切断的態度の内にある。サディズムは自分と似た他者を切断する行為によって虚無を回避し大いなる他者を現出させようという涙ぐましい努力である。三島は映画の中でも言っているように、その他者は天皇である必要はなかった。本来的になんでもよいが、卒業式で時計をもらったときの天皇はとてもご立派だった、そういう個人的恩顧が三島にはあった。
三島の学生への問題提起は、物と持続についてであった。机は本来の使用用途とは別の扱いを受けることがある。たとえばバリケードのように。究極的には何者でもないことは可能なのか、という問いである。革命が本来の使用用途や存在様式から離れることであるとして、それを持続させることは原理的に可能なのか、ということである。成功するかどうかは問題ではないと言ったときに無自覚であるのはどういった点か。それは何者でもないということは不可能であるということだろう。常にすでに、人は何者かになってしまっている。同時に物はある眼差しの中でそれが本来的とよび得るか非本来的とよび得る在り方かどうかによらず何物かであってしまっている。
学生たちが他者と思しい権力と対峙するなかで、三島の問題意識は他者がいないこと、大いなる他者が不在であるということにあった。だから三島の学生に対する問いは、転覆した先の他者をどう担保するのか、ということでもあっただろう。というより、他者は大なり小なりおらずにはおれないものではあるが、君たちのそれは私が天皇と名指すものに匹敵し得るものなのか、どうなのかということだろう。大澤真幸は『三島由紀夫 ふたつの謎』の中で三島の原点、出発点に「一の内的不可能性」があったということを書いている。少し引用する。
こんなふうに問いを立ててみよう。もし究極の真実が『豊饒の海』の結末が示唆しているように、容赦のない虚無であるならば、つまり「0(ゼロ)」であるならば、どうして何かが、世界が存在するのか。
究極の真実は、虚無、つまり「0」とは異なる何かではないか。見まちがうほどによく似てはいるが、「0」とは異なる何かではないか。それを、ここでは「一の内的不可能性」と呼んでおこう。…
私は学生の頃、戯れに0∞システム(ゼロ無限システム)というものを考えたことがあった。虚無であるところの人と無限大であるところの絶対的存在からキリスト的一が析出し得るという信念に基づく体制をそう呼んでみた。0∞=1は可能性の海であるが、それは幻想に過ぎない。このシステムは人が限りなく0か無限大に近づくことで有1であるところの1を体現できるという信念があって初めて駆動するが、実際にはこの1は遡及的にしか見出されない代物であるが故に不可能である。
0∞=1の地平で闘っても資本主義やキリスト教は乗り越えられないということをおそらく三島は自覚していた。0∞≠1と否を叩きつける存在を三島は強く求め、その存在として天皇を選んだ、ということではないか。
三島は自我が極端に肥大し風景の隅々にまでそれが侵食したような小説を書く一方で、自我を極度に希釈させてみせるような試みもする、その所作はゼロと無限の間を焦慮に駆られながら気忙しなく振幅しているようにも見える。
私たちは常にすでに1であり、そこから逃れることはできない。何ものでもない在り方や何ものでもある在り方を求めることはシステムにとっては織り込み済みの行為であり、それこそが資本主義の糧となっている。私は何ものでもないとか、何ものにでもなり得るという態度は、だから態度として至極「合法的」といえる。三島がいう非合法的暴力は0でもなく無限大でもなく0を反転させた形での無限大でもなく無限大を反転させた形での0でもなく、それらのスペクトラムとは全く無関係に有無を言わさず新たに1を穿つ行為のことではなかったか。それが三島の小説においても実際の行動においても成功しているとは思えないが。
基礎に立ち返ると、1はやはり穿つものではなくすでに穿たれたものとして立ち現れる。あらゆる、多様な1が可能だが、穿つことはできない。それと知らずに1となっている、活動とはそういうものではないか。1を目指すことはできないし、そもそもその目指す行為は意図せずその人を双数関係へと導いてしまう。
ジジェクは平等と認識される正義は妬みの上に成り立っているという(スラヴォイ・ジジェク『パンデミック2 COVID-19と失われた時』)。能力に応じて働き、必要に応じて受け取る、ということは平等主義とは異なる。問題なのは序列や格差が自由や平等の名の下にうまれていることだろう。三島は持続を問うていた。それは机をバリケードたらしめる行為者への責任を問うことでもある。たとえば、あなたたちはバリケードであると言った場合、その眼差しが持続しないのであれば机は絶えず名指すものの顔色を伺っていなければならなくなる。持続しないこの暴力は三島の言葉を借りれば合法的な暴力ということになるだろうか。織り込み済みの暴力である。ベンヤミンの説いた神話的暴力(法維持的暴力、法措定的暴力)と神的暴力の分類でいうと、機動隊の暴力は法維持的暴力で学生の暴力は法措定的暴力にあたるだろう。三島はそれとは別の神的暴力を発動させたかった、のではないか。
それは天皇である必要はなかったと三島は言う。私は近所のおじさんでもNPOでもいいと考えている。おじさんだろうがNPOだろうが気づいたら1になっている、ということがあるだろう。 (2021.06.14)
一般公開されている作品や著作物について、紹介・考察していきます。